国語科:新たな世界を拓く言葉の力
目標と養いたい力
国際社会でよりよく生きるために、物事に対する洞察力、自己と他者とを深く理解するためのコミュニケーション能力、確かで豊かな表現力を養うとともに、言葉・文化に対する興味・関心を高める。
単位数
| 学年 | 科目名 | 時数 | 主な内容 | 単元例 【 】内は主なテキスト |
| 1 | 国語 | 4 | 表現の基礎 読解の基礎 言葉の基礎知識の獲得と活用 |
◇随筆の真髄にふれようー「字のない葉書き」ラジオドラマ【向田邦子「字のない葉書き」(随想)】 ◇語りには意図が含まれる【小関智弘「ものづくりに生きる」(説明)】 |
| 2 | 国語 | 4 | 表現の基礎と発展 読解の基礎と発展 言葉についての知識の獲得と活用 情報と表現 |
◇表現するとはどういうことか【太宰「走れメロス」(小説)・シラー「人質」(詩)】 ◇見ぬ世の人との対話-戦や人々の生死が物語として語られる意味【「敦盛の最期」(平家物語)(古典)】 |
| 3 | 国語 | 3 | 表現の活用 読解の深化 言葉についての知識の獲得と発展・応用 情報の活用 |
◇効果的な表現を用いてリポート記事を書く【雑誌記事、エッセイ集】 ◇文学的文章を論理的に読む【井上ひさし「握手」(小説)】 ◇俳句を詠む【「俳句十五句」(俳句)】 |
| 4 | 現代の国語 | 2 | 日本語の特色を理解し、基礎的な国語の力を充実させる。 | ◇私たちの世界を作る言葉 ◇多様な文化の中のコミュニケーション ◇「論理」とは何か ◇言葉の可能性と限界 ◇概念を形成する言葉 |
| 4 | 言語文化 | 2 | 言語文化への理解を深め、基礎的な国語の力を充実させる。 | ◇小説の本質とは ◇文化とコミュニケーション ◇メディア情報リテラシー ◇詩歌の型と伝統 ◇思想や論の読み比べ |
| 5 | 論理国語 | 4 分割履修 各年度2単位 |
実社会において必要とされる批判的に分析する力や、自らの考えを論理的に構成する力を養う。 | ◇言語と世界の認識 ◇社会のシステムと人間 ◇科学技術と人間 ◇複数の文章を比較する観点 |
| 5 | 文学国語 | 4 分割履修 各年度2単位 |
多彩な文学的文章の学習を通して、語感を磨き、表現や言語文化に対する理解を深め、ものの見方や考え方を深める。 | ◇翻案と作者のフィルター ◇言語文化の変化、文学の社会的機能 和歌・短歌、歌物語 ◇個人的・社会的経験と虚構としての表現 ◇メタファーの成立・寓話の機能 史伝、小説 |
| 5 | 古典探究 | 4 分割履修 各年度2単位 |
古文・漢文の学習を通して、伝統文化についての関心を高め、理解を深める。 | ◇時間と空間はテキストの世界にどのように影響するか。 ◇古典と近代の文学の主題はどのように異なるか。 (テキスト故事・漢詩・史伝・詩背負う・小説・日本の漢詩文) (テキスト 説話・随筆・物語・和歌・日記) ◇古漢の比較や、近代以降の文章との比較を通して探究的に学びを深める。 |
| 5・6 | DP文学 | 各年度5単位×2 | 文学の学習を通して、言語表現の多様な可能性について学ぶとともに、文学を通してグローバルな問題に迫る。 | ◇HL13作品(翻訳作品4つを含む)を扱う。例:『地獄変』『ペスト』『源氏物語』『謡曲集』『近代能楽集』『わたしを離さないで』『日の名残り』『野火』『砂の女』『予告された殺人の記録』『沈黙』『セールスマンの死』『人形の家』『春琴抄』『谷川俊太郎詩集』『山月記・弟子』『論語』等 *これらは現在のクラスでは使っていないものも含んでいます。 |
| 6 | 論理国語 | 4 分割履修 各年度2単位 |
実社会において必要とされる批判的に分析する力や、自らの考えを論理的に構成する力を養う。 | ◇言語と世界の認識 ◇社会のシステムと人間 ◇科学技術と人間 ◇複数の文章を比較する観点 |
| 6 | 文学国語 | 4 分割履修 各年度2単位 |
多彩な文学的文章の学習を通して、語感を磨き、表現や言語文化に対する理解を深め、ものの見方や考え方を深める。 | ◇翻案と作者のフィルター ◇言語文化の変化、文学の社会的機能 和歌・短歌、歌物語 ◇個人的・社会的経験と虚構としての表現 ◇メタファーの成立・寓話の機能 史伝、小説 |
| 6 | 古典探究 | 4 分割履修 各年度2単位 |
古文・漢文の学習を通して、伝統文化についての関心を高め、理解を深める。 | ◇時間と空間はテキストの世界にどのように影響するか。 ◇古典と近代の文学の主題はどのように異なるか。 (テキスト故事・漢詩・史伝・詩背負う・小説・日本の漢詩文) (テキスト 説話・随筆・物語・和歌・日記) ◇古漢の比較や、近代以降の文章との比較を通して探究的に学びを深める。 |

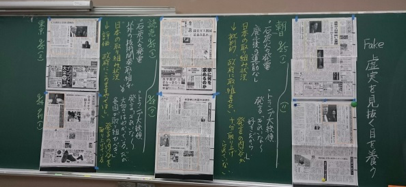

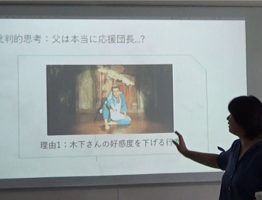
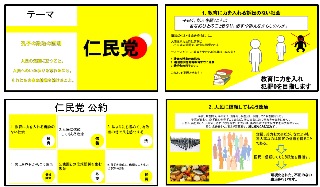
 毎年11月に都内の能楽堂を訪れ、能や狂言を鑑賞し、日本文化の歴史や面白さに触れています。謡(うたい)の体験などもあり、衣装を実際に身に付けて舞台に上がり所作を教えて頂き、能の面(おもて)を付けてみる経験もします。
毎年11月に都内の能楽堂を訪れ、能や狂言を鑑賞し、日本文化の歴史や面白さに触れています。謡(うたい)の体験などもあり、衣装を実際に身に付けて舞台に上がり所作を教えて頂き、能の面(おもて)を付けてみる経験もします。